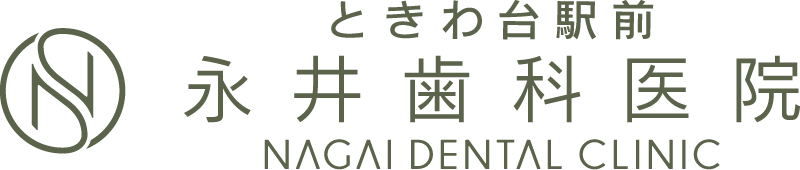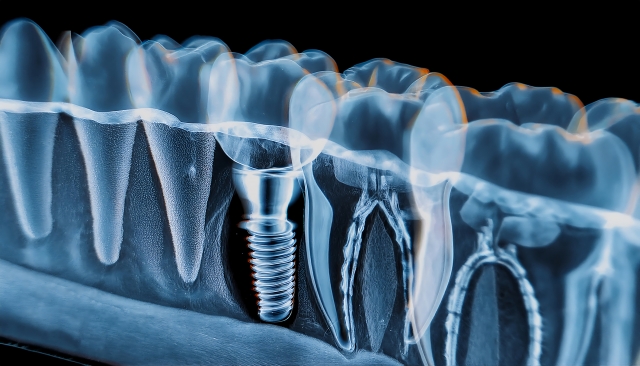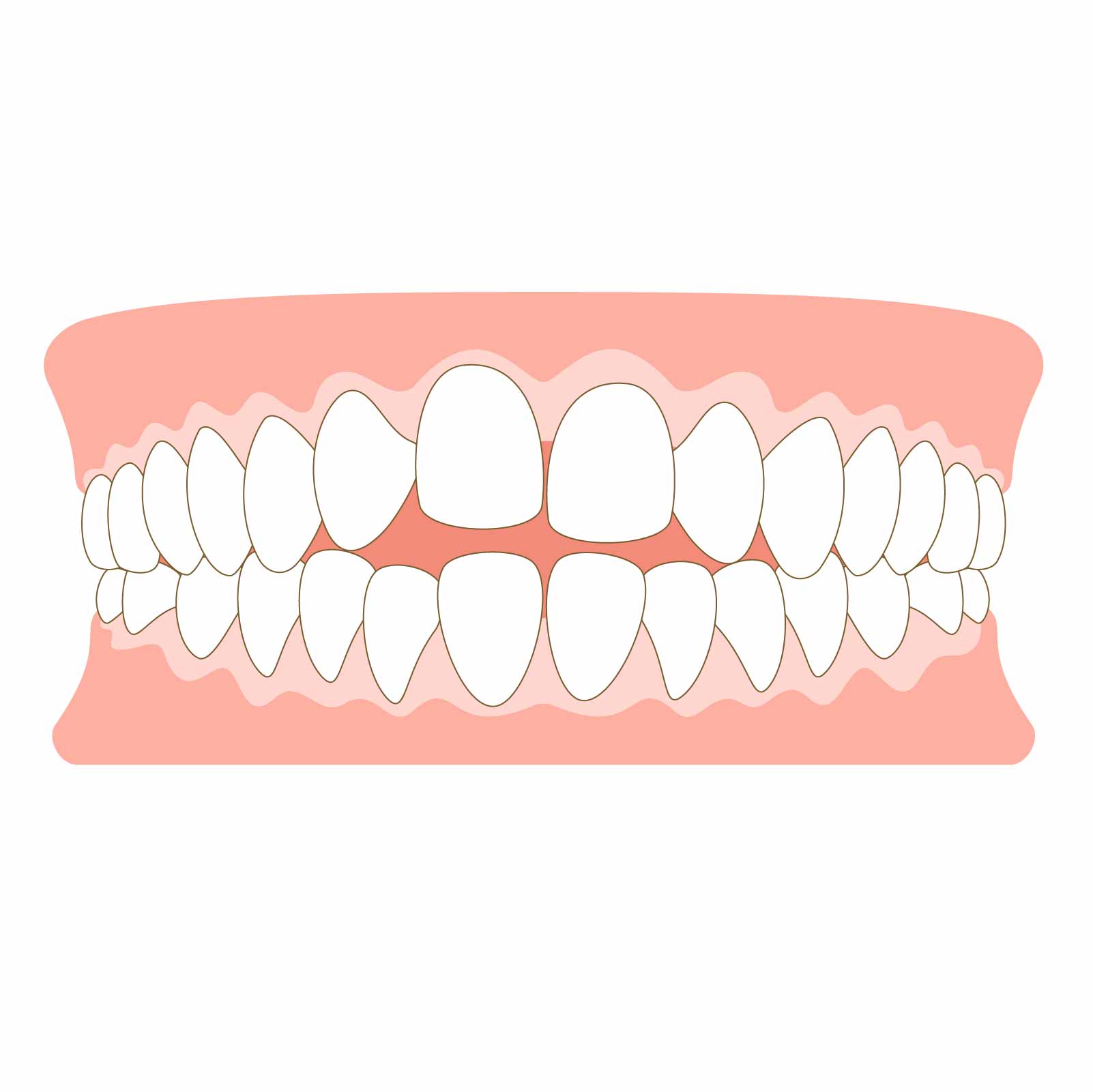2025年10月17日

「最近、あごが疲れる」「肩がこる」「朝起きてもすっきりしない」——そんなお悩みはありませんか?
一見すると関係のないように思えるこれらの症状が、実は“噛み合わせ”の乱れに由来していることがあります。
噛み合わせとは、上下の歯がどのように接触し、力を分散しているかという関係のことです。食事や会話のときだけでなく、無意識のうちにもあごは働いています。わずかなズレであっても、あごの関節や周囲の筋肉に負担がかかり、体全体のバランスが崩れることがあるのです。
噛み合わせが悪くなる原因
噛み合わせの乱れは、さまざまな要因によって起こります。代表的なものとしては、
・虫歯や歯周病で歯を失ったまま放置している
・合わない被せ物や詰め物を長年使用している
・歯ぎしりや食いしばりの癖がある
・姿勢の悪さや頬杖など、日常的な習慣
・矯正治療後の後戻りや、成長期のあごのズレ
などが挙げられます。
これらの要素が重なることで、上下の歯が自然な位置で咬み合わなくなり、顎関節や筋肉に負担がかかります。最初は違和感程度でも、次第に全身へと影響が広がっていくことも少なくありません。
噛み合わせの悪化で起こる主な不調
噛み合わせの不調によって現れる症状は、口の中に限りません。
1. 顎関節の痛みや音
顎の関節がずれた状態で動くため、「カクッ」と音がしたり、口を開けると痛みを感じたりします。これを「顎関節症」と呼び、噛み合わせとの関係が深い症状です。
2. 筋肉のこりや頭痛
噛み合わせがずれると、咀嚼筋(そしゃくきん)や首・肩の筋肉に常に余分な力がかかります。その結果、慢性的な肩こりや緊張型頭痛を引き起こすことがあります。
3. 歯や歯ぐきへのダメージ
一部の歯にだけ強い力が集中すると、歯がすり減ったり、知覚過敏や歯周病の悪化につながったりします。
4. 姿勢の乱れや全身のバランスの崩れ
噛み合わせは頭や首の位置とも密接に関係しています。あごがずれると、体全体のバランスも崩れ、猫背や体のゆがみを引き起こすことがあります。
5. 集中力の低下や疲労感
慢性的な筋緊張や痛みは、自律神経にも影響します。噛み合わせの不良が原因で、なんとなく疲れやすい・眠りが浅いといった不調を訴える方もいらっしゃいます。
早めの診断・治療が大切です
噛み合わせの異常は、自分ではなかなか気づきにくいものです。「歯は痛くないのに、なんとなく違和感がある」と感じたときこそ、歯科で一度チェックすることをおすすめします。
当院では、あごの動きや筋肉のバランス、歯の接触状態などを丁寧に確認し、原因を総合的に判断します。必要に応じて、咬み合わせの調整、マウスピースの装着、被せ物の再製作、矯正治療などを組み合わせて治療を行います。
日常生活で気をつけたいポイント
治療だけでなく、日頃の生活習慣の見直しも大切です。
・頬杖やうつ伏せ寝を避ける
・スマートフォンを見るときの姿勢を意識する
・強く噛みしめる癖に気づいたら、力を抜く習慣をつける
・歯ぎしりがある場合はナイトガード(マウスピース)を使用する
小さな意識の積み重ねが、噛み合わせの改善にもつながります
噛み合わせを整えることは、健康を整えること
噛み合わせの不調は、単なる「歯の問題」にとどまらず、全身の健康にも影響を及ぼす重要な要素です。肩こりや頭痛がなかなか改善しないとき、「もしかして噛み合わせが関係しているかも」と考えてみてください。
お口の状態を整えることは、体のバランスを整えることにもつながります。気になる症状がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
監修:永井歯科医院 院長 永井 太一